1970年代、プロテインはボディビルダーやパワーリフターなど限られた層にしか知られていない存在でした。1990年代になると野球・サッカーといったメジャースポーツの選手が利用し始めたことで市場が拡大。2000年代になると日常的に筋トレをする方や美意識の高い女性などさらに拡大し、身近なものとなってきました。
そして2020年現在、健康ブームはさらに加速し、さまざまな用途で老若男女問わずプロテインを活用する時代となりました。また薬局やネットショップなどでいつでも購入でき、生活の一部として浸透してきています。
市場の拡大が広がる一方、プロテインを飲むことによる下痢やおならなどの不調を訴える声。人体への影響を心配する声など、「副作用」についても関心が高まっているようです。今回は、そのような不調に対する項目をまとめ、詳しく解説していきます。
プロテインによる悪影響

人体にとって悪影響を及ぼす作用は一般的に「副作用」と呼ばれますが、そもそも副作用という言葉は、「薬」に使う用語です。薬には、ある症状(病気)を抑えるために必要な成分が含まれています。よって効果は十分あるのですが、ターゲットにとどまらず、その他にも作用してしまうことを「副作用」といいます。
前提としてプロテインは「食品」です。またプロテイン以外にサプリメントなどの「健康食品」が販売されていますが、それらは「健康な人」を対象としています。確かに、プロテイン市場が拡大し、不調をきたす声もあがっているようですが、それらを一言で「副作用」という言葉で片づけてしまうのは不適切です。
例えば、さつま芋を食べると「おなら」が増えることは有名なお話ですね。それを「さつま芋の副作用」といわないのと同じことです。
それではプロテインを摂取したことによって起きたであろう、あまり嬉しくない事例についてご紹介します。
下痢・おならの増加
下痢・おならの増加については、
- プロテインが自身の体質にあってない
- 乳糖不耐症
- 腸内細菌の乱れ
が考えられます。
現在市場に出回っているプロテインの多くはホエイプロテインというものです。ホエイプロテインの原料は牛乳です。この牛乳に含まれる乳糖(ラクトース)を消化する酵素(ラクターゼ)の分泌が少ない、または欠乏している場合は、乳糖を消化できないために下痢などの消化不良を起こします。
もともと、日本人はラクターゼが少ない人種といわれており、牛乳を飲んでお腹を壊す人が多いのは、酵素の影響といわれています。合わないのであれば、ソイプロテインなど牛乳以外の原料でできているプロテインがおすすめです。
もう一つが腸内細菌の乱れです。腸内細菌には、善玉菌、悪玉菌、日和見菌が絶妙なバランスで働いています。しかしこのバランスが崩れると、下痢や便秘を起こしてしまう可能性があるのです。
今まで飲んでいなかったプロテインを急に飲みだしたことでバランスが崩れたのか?「いざ、筋トレ」と意気込みプロテインばかりに食事が偏ることによる食物繊維不足?など、要因はいくつか考えられますが、腸内環境のバランスが崩れているのかもしれません。
おならは、口から飲み込んだ空気と食物が腸内で消化されるときに生じるガスが原因で発生するといわれています。なるべく「ガスを飲み込まない、腸内でのガス発生を抑制」することがポイントです。プロテイン及び食事からタンパク質を過剰に摂取すると、消化する際に腸内でガスが大量に発生するので注意が必要です。
また「ガスを飲み込まない」ってそんなこと難しいってなりますよね。実はプロテインの攪拌(かくはん)を工夫することで空気の量を抑えられます。詳細は下記記事をご覧ください。
プロテイン摂取による「おなら」と「下痢」についての解説とその予防法
肌荒れ・ニキビ
プロテインには、カラダの材料となるアミノ酸が20種類含まれているので土台を築くうえでおすすめです。
その一方で、肌荒れやニキビを訴える人もいるようです。そもそもニキビの原因は、
- 遺伝
- ホルモン
- 異常な角質化
- 食生活
などさまざまです。食生活については議論真っ只中ですが、糖質や牛乳の過剰摂取があまりよくないといわれています[1]。
またホエイプロテインが何かに影響しているのではないかといわれていますが[2]、まだまだ研究数が少なく明確なことは断言できません。
太る原因にもなる
市販されている多くのプロテインは「高タンパク・低脂質」。カラダづくりに活用しやすいように設計されています。しかしながら「プロテインを飲み始めたら太りました」と度々相談をうけます。
その答えは簡単です。
- プロテインの飲みすぎによるエネルギー摂取過剰
- 摂取量に対しての運動量(消費量)が見合ってない
この2点です。
下に1日に必要なエネルギー量を示しました。自身がどれくらい1日にエネルギーを必要とするのか、それに見合った量を食事から、不足する場合はプロテインから取り入れることが大前提です。
市販されている多くのプロテインは、低脂質のものが多いです。しかしタンパク質も過剰分は体脂肪として蓄えられますので、沢山飲んでいては太ります。
またプロテインを牛乳で割る方もいらっしゃいますね。エネルギー量やタンパク質量を増したい方には有効ですが、牛乳1杯(200ml)には唐揚げ約2個分の脂質が含まれています。体重が気になる方は水で割りましょう。
またプロテインを飲むだけで満足していては勿体ないです。運動により筋肉に刺激を与えることで、効率的にタンパク質を取り込めるので、プロテインを飲んだら運動することをおすすめします。
推定エネルギー必要量(kcal/日)
厚生労働省 日本人の食事摂取基準(2020年版)より作成[3]
臓器への影響(肝臓・腎臓)
タンパク質は肝臓と腎臓で分解されるので、特に過剰に摂取している方は、腎臓や肝臓に負担がかかっている可能性があります。
さらに注意が必要なのは、肝臓や腎臓に持病をお持ちの方です。病気をお持ちの方は、過剰摂取に関係なくタンパク質摂取には注意が必要です。通常、タンパク質を摂取した場合、肝臓と腎臓がうまく機能して分解します。その際に体内に必要な成分とそうでないゴミを区別して、必要でないものは尿へ排泄する仕組みとなっています。
一方、病気の場合は、そのサイクルが円滑におこなえないので、かえって負担となってしまうことがあるのです。実際に、腎臓病食や肝臓病食といって、食事も治療の一環となっており、食事に含まれるタンパク質の摂取を控えることもあります。食事療法をおこなうにあたり、医師や管理栄養士が個々人の病気の状態を十分に把握して、適切なアドバイスをおこなっています。
現在、加齢によるフレイルやサルコペニア対策で高齢者にもタンパク質摂取が推奨されています。しかし特に高齢者は、さまざまな疾患を合併されている方が多く、安易にプロテインに手を出すことは推奨できません。持病をお持ちの方は、必ず医師に相談のうえで判断されることをおすすめします。
プロテインは「健康な人」を対象に製造されている食品です。牛乳や肉などとは異なり、1食でそれらの何倍ものタンパク質を摂取できますが、それがかえって臓器への負担となることもあります。
私たちプロテインユーザーにできることは、健康診断などで最低でも年に1回、自身の健康状態をチェックしながら、プロテインを適切に扱うことではないでしょうか。
タンパク質の適正量を知る
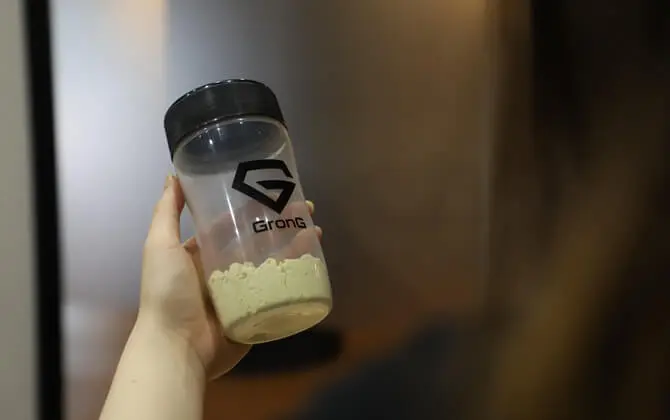
今まで、紹介した嬉しくないプロテインの悪影響の部分について紹介しましたが、自身の体質にあわない場合を除き、適切な量を知り・扱うことで改善される可能性があります。
タンパク質については、一般的に1日に男性60~65g、女性50g、必要とされています[3]。日頃からトレーニングを積極的におこない活動量が多い方は、活動量に応じて1.4~2.0/kgを目安に摂取するとよいでしょう。また1回に過剰に摂取すると消化不良の原因となることもあるので、1回あたり0.25/kg程度のタンパク質摂取をおすすめします。
「えっ?1回量が少なくて、1日分確保できないじゃないか?」と疑問をもたれる方は、下記記事をご覧ください。トレーナーが摂取量やタイミングについて徹底解説しています。
タンパク質を適切に取り入れるためのポイント
- 1日にどれくらいの量が必要か知る。
- 基本は3食の食事でタンパク質を取り入れる。不足分をプロテインで+α
まとめ
今回はプロテインを摂取することによる悪影響をご紹介しました。プロテイン需要が高まるとともに、多くの情報が錯綜し、悪影響についても関心が高まっているのも事実です。
しかしこれは、良い流れであると考えています。プロテインを活用するにあたり、「メリットよりもデメリットを知る」ことがとても重要で、両者を認識したうえで活用することが大切です。
自身の体質と合わないことを除き、過剰摂取や食事バランスの乱れが悪影響の原因であることが多いです。そのため適切に対処すれば、デメリットを極力抑えながらプロテインを摂取できるのではないでしょうか。
最後に、プロテインは「健康な人」を対象とした食品です。持病をお持ちの方は、くれぐれも安易に手を出すのではなく、医師に相談し判断することを推奨します。それが身体を守る最善の策ではないでしょうか。
参考文献
1. Pappas, A. (2009). The relationship of diet and acne: a review. Dermato-endocrinology, 1(5), 262-267.
2. Pontes, T. D. C., Fernandes Filho, G. M. C., Trindade, A. D. S. P., & Sobral Filho, J. F. (2013). Incidence of acne vulgaris in young adult users of protein-calorie supplements in the city of João Pessoa-PB. Anais brasileiros de dermatologia, 88(6), 907-912.
3. 厚生労働省. 日本人の食事摂取基準(2020 年版)
この記事を書いた人

坂口 真由香
管理栄養士、日本糖尿病療養指導士、フードコーディネーター、サプリメントアドバイザー保有。大阪市内400床病院で6年間、献立作成や慢性期から急性期疾患の栄養管理に従事。糖尿病などの慢性疾患を対象に年間4,500件ほどの栄養相談・サポートを経験。




