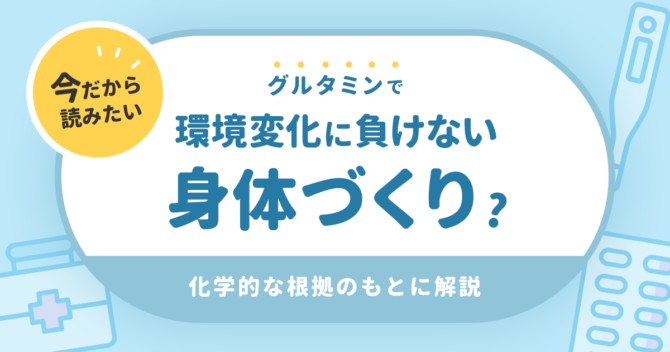リカバリーの栄養素!グルタミンと筋トレの深い関係とは?

「寝る子は育つ」といいますが、子どもって本当に驚くくらいよく眠りますよね。睡眠は身体を回復させるために重要な要素のひとつ。また、睡眠と同じくらい大切なのが栄養です。
「睡眠」と「栄養」の質が高い人は、回復がスムーズになることで日中も精力的に活動できます。そしてなにより健康的な生活を送れます。
ハードに筋トレをする人は、年齢を重ねれば重ねるほど、トレーニングと同じくらい「いかにリカバリーをするか」がカギになってきますからね。
今回のコラムでは、睡眠と栄養において重要な役割を持ち「身体を守るアミノ酸」ともいわれるグルタミンと筋トレの深い関係についてお伝えします。
グルタミンの働き

刺激に対抗する身体づくりに
体内におけるグルタミンの働きは「外的負荷から身を守るためのエネルギー」です。負荷と聞くと、マイナスなイメージを持たれるかもしれません。実際に、生きていく上で身体にかかる負担や刺激は「ストレッサー」と呼ばれ、必要なものなのです。
人間関係の精神的負担はストレスの象徴のような存在ですし、「会社での重要なプレゼン」や「人前に立って歌う」などある種の緊張する場面もストレスにあたります。そしてあなたが一生懸命取り組んでいるであろう「トレーニング」も、実は身体を成長させるための肉体的なストレスです。
これらすべてのストレスは適度であれば必要なものなのです。
どんな刺激も過剰になれば身体にとってよくない負担になってきます。その刺激に負けない身体づくりのためにはグルタミンの力が必要になります。
丈夫な身体の維持に
グルタミンは外的刺激に対抗するためのエネルギーと前述しました。
グルタミンは身体を守るために欠かせない栄養素なのです。忙しく余裕のない社会生活を送る上に、筋トレなどで肉体的な負担が多くなると、通常よりもグルタミンの消費量がグンと増えます。適切な補給をすることで、丈夫な身体をキープするようにしましょう。
筋トレとグルタミンの関係

とくにアスリートやトレーニーにとっては、せっかく鍛えた筋肉が減るのだけは避けたいところ。筋トレ用語で「カタボる※」といったりします。少しわかっている人に使えば通じる言葉です。
※ カタボリック(Catabolic)⇒体内の組織を分解する代謝作用。異化作用ともいう。
運動のエネルギーは糖質と脂質が中心。とくに筋力トレーニングのエネルギー源は主にグリコーゲン(糖源)です。肝臓や筋肉に貯蔵していたり、血中に流れる糖を利用します。
運動強度が高かったり、運動時間が長くなるにつれて、体内にあるエネルギー源だけでは供給が追いつかなくなるため、自らの筋肉を分解(糖新生)して運動のエネルギーを生み出そうとします。身体のメカニズムってすごいですね。
筋トレのジレンマともいえるでしょうか。身体を鍛えることで筋肉を合成(成長)させようとするスイッチが入ると共に、分解しよう(ストレスから守ろう)とするスイッチも入るのです。
筋肉が大きくなるには合成が分解を上回る必要があります。そこで筋肉の材料となるタンパク質やアミノ酸の出番です。とくにグルタミンには、刺激からの身を守るための丈夫な身体づくりのサポートとして報告されています[1]。
理想の身体づくりには、血中のアミノ酸量を一定間隔で十分に満たしておく必要があります。バランスのよい食事に加えて適切なタイミングでの間食が必要になるでしょう。
間食の目安は「トレーニング後から次の食事までの間」「最後の食事から就寝前までの間」にとるようにするのがオススメです。
まとめ
筋トレが好きな人よりも苦手な人のほうが多いでしょう。身体を鍛えることは、それだけ身体に負担がかかることでもあります。
しかし適切に栄養を補給してあげることで、運動刺激による筋肉合成に必要な材料となり、日ごろのエイジングケアにつながったりと良い面があるのも確かなことです。
古代の王様が求めた「不老不死」までは叶わないにしても、より良く自分の人生を生きるためには、運動のリカバリーに取り組んでみるのがよいかもしれませんね。
参考文献
1. Petra G. Boelens, Robert J. Nijveldt, Alexander P. J. Houdijk, Sybren Meijer, Paul A. M. van Leeuwen, Glutamine Alimentation in Catabolic State, The Journal of Nutrition, Volume 131, Issue 9, September 2001, Pages 2569S–2577S,