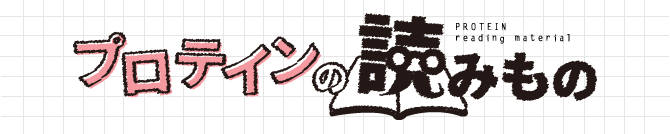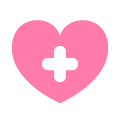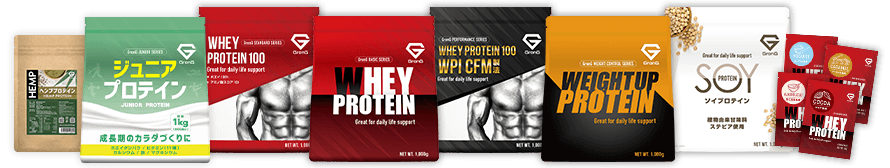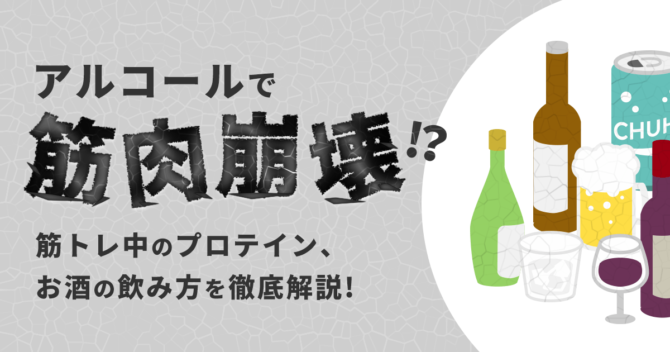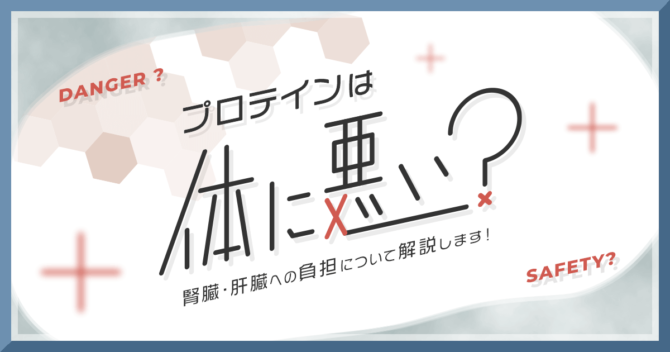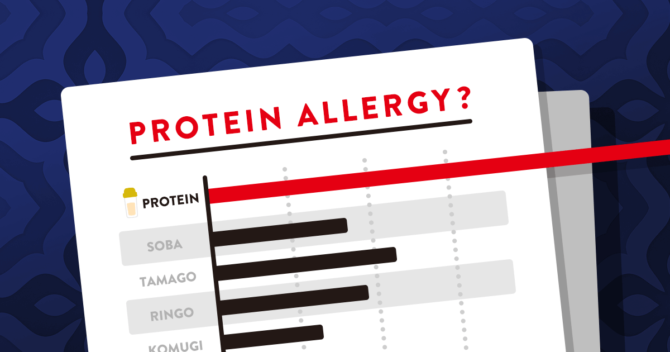プロテインを飲んで腹痛や胃痛が起こる原因と対策
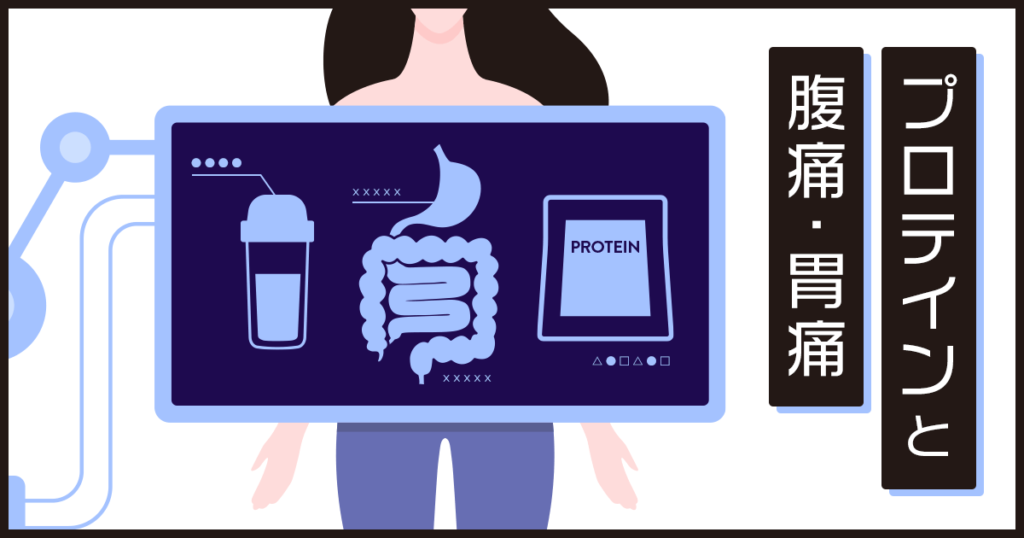
冷たい牛乳を飲んだら、お腹がゴロゴロとしたことありませんか?胃やお腹に痛みや不快感が出ると、気分まで下がってしまいますよね。
ホエイプロテインの原料は牛乳です。プロテインユーザーから、プロテインを飲むとお腹が痛くなったり、胃がムカムカしたりするという声を聴くことがあります。身体に良いはずの食品が、どうして胃痛や腹痛につながってしまうのでしょうか。
その原因はプロテインにあるのか?それともお腹や胃腸などの身体にあるのか?今回はプロテインとお腹の関係について解説します。
プロテインで腹痛や胃痛になる原因

乳糖不耐症の可能性
プロテインの中でも主流なのは、牛乳を原料としたホエイプロテインやカゼインプロテインです。牛乳には乳糖(ラクトース)という成分があり、体内での消化にはラクターゼという酵素が必須です。
しかし人を含むほとんどの哺乳類は離乳と共に、このラクターゼの活性は低下していきます。成人になっても、ラクターゼの活性を高い水準でキープしている人の割合は、国や地域によって異なりますが、牧畜が盛んな文化を持つ国の人は比較的ラクターゼの活性が高く、そうでない国の人は低いという研究報告もあります[1]。
つまり身体に入ってきたのはいいけれど、消化するための酵素がない……。この症状を「乳糖不耐症」といいます。
具体的には、消化できなかった乳糖が大腸に流れ込むことで、大腸内の浸透圧※1が上昇します。余分な水分を体外に排出しようとした結果が「下痢」につながるのです。
ホエイプロテインやカゼインプロテインを飲むと高い確率で下痢や腹痛を起こす場合、この「乳糖不耐症」である可能性が考えられます。
※1 浸透圧:細胞膜や毛細血管の壁、尿細管の壁などは半透膜という組織で隔てられています。細かい分子は通過でき、タンパク質などの大きい分子は通過できないのが特徴です。体内の液体はバランスを調整するため、濃度の低い方から高い方へと移動する性質があり、このときに半透膜にかかる圧を浸透圧とよびます。
腸内環境
腸には細菌がおよそ1,000種類、100兆個以上も存在するといわれており、腸内細菌のバランスが健康状態に大きく影響すると考えられています。また「脳腸相関」といって、腸内環境(善玉菌、日和見菌、悪玉菌のバランス)が自律神経やホルモンの調整に関係していることも明らかになってきました[2]。
一度に摂取できるタンパク質量には限界があります。プロテインが筋肉の材料であるからといって、一度に大量に摂取すると、消化吸収しきれなかったタンパク質は腸内に送られることになります。
余分なタンパク質は「悪玉菌」の格好のエサとなります。悪玉菌はタンパク質を腐敗させ、有害物質(ガスや発がん性物質)が発生することで、腸内環境が乱れてしまうのです。
これらにより便秘や下痢、腹部膨満感など胃腸にまつわるトラブルを起こしやすくなってしまいます。
摂取するタイミング
「プロテインを夜に飲むとよい」と聞いたので、寝る直前に飲んている方もいらっしゃるかもしれません。しかし飲食をした後、すぐに横になると胃腸への負担が大きくなります。
「逆流性食道炎」といって、強い酸性の胃液や胃で消化される途中の食物が、逆流することで食道が炎症を起こし、胸やけや胸の痛みなどの症状があらわれる病気を引き起こしやすくなります。
また「トレーニング後すぐにプロテインを飲まないといけない!」ということにこだわり過ぎて、トレーニング直後に息が上がったままプロテインをゴクゴク飲むことも負担が大きくなる原因です。
運動後、交感神経が優位な状態の身体は、胃腸の活動が低下している状態です。「ゆったりシャワーを浴びて、着替えを済ませてからでも間に合う」くらいの気持ちでいたほうが、交感神経の興奮がおさまり、胃腸も活動しやすくなるため、身体への負担は少なくなります。
不快感を抑えるプロテインの選び方・飲み方、その他方法
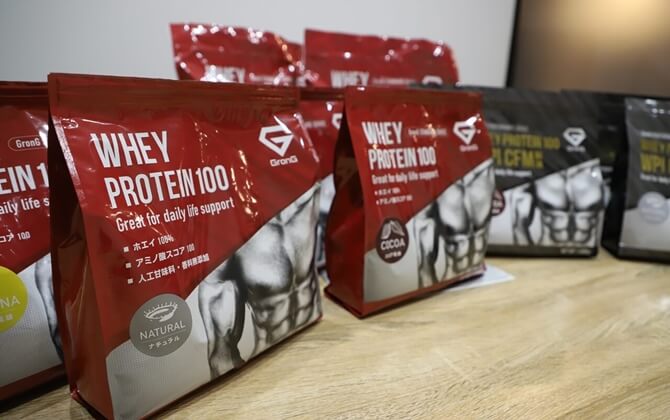
乳糖不耐症の可能性がある方
WPI製法のホエイプロテインを選ぶ
WPI製法のプロテインは、WPC製法のプロテインよりもタンパク質の含有率が高く、乳糖が少なくなっています。少し割高ですが、乳糖不耐症の可能性がある方には、WPI製法のプロテインがおすすめです。
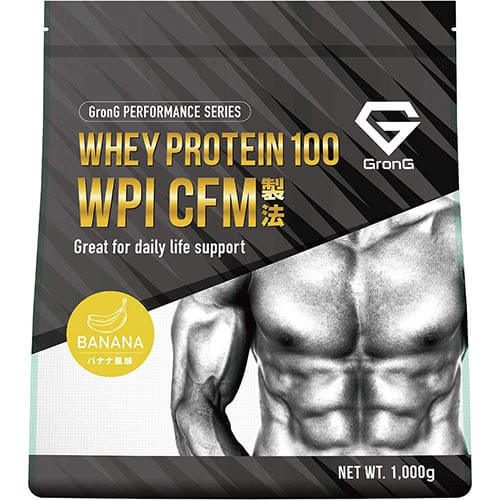
大豆が原料のソイプロテインを選ぶ
乳糖不耐症の方には、乳糖が含まれない大豆を原料としたソイプロテインもおすすめです。ソイプロテインに含まれる食物繊維は、身体づくりをサポートしてくれます。
腸内環境が気になる方
生きた善玉菌「プロバイオティクス」を直接摂取する
- ヨーグルト
- 乳酸菌飲料
- 納豆
- 漬物
など、「ビフィズス菌」や「乳酸菌」を食事に取り入れましょう。
善玉菌を増やす作用のある「プレバイオティクス」を摂取する
- 野菜類
- 果物類
- 豆類
などに多く含まれる「オリゴ糖」「食物繊維」を食事に取り入れましょう。
便の状態を欠かさずチェックする
善玉菌がよく働いているときは、黄色から褐色の便で、匂いがあっても臭くなく、形状は柔らかいバナナ状が理想とされています。
反対に黒っぽく濃い色で悪臭がある便は、腸内細菌のバランスが悪くなっている状態ですので、観察の目安にしましょう。
胸やけや腹部膨満感が気になる方
少量を数回に分ける
一度に大量のプロテインを摂取することで、お腹が張ったり下痢をしてしまう方は、数回に分けて摂取することをおすすめします。吸収の効率を上げると同時に、内臓の負担を減らせます。
時間を空ける
トレーニング直後に摂取して不快感のある方は、身体の興奮を抑えるために少し時間を空けるようにしましょう。クールダウンやシャワーを済ませても効果的な摂取は十分に可能です。呼吸を整え、落ち着いてからゆっくりと味わいましょう。
夜の摂取で不快感がある方は、プロテインが消化吸収される時間を考慮して、ベッドに入る1~2時間前に摂り、少しお腹を休ませてから横になるようにしましょう。
まとめ
「You are what you eat.(あなたはあなたの食べたものでできている)」
という言葉があります。栄養は身体をつくるうえで、大切なものです。
特にタンパク質は身体に不可欠な栄養素の代表格です。三食のバランスの良い食生活を基本としたうえで、うまくプロテインを活用すると、あなたの身体づくりのサポートを一役買ってくれることでしょう。
身体はとても賢く、もし身体に不調があれば「痛みや不快感」というかたちで知らせてくれます。身体からのSOSは、不調を見直すためのヒントだと考えてみましょう。
自分の身体を知ることは、自分が食べたものや食べ方を知ることでもあるのです。
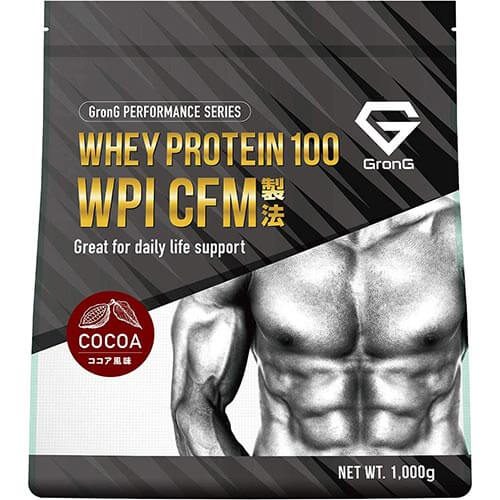
参考文献
厚生労働省. 腸内細菌と健康 | e-ヘルスネット. 閲覧2020-06-06, https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/food/e-05-003.html